【体験談】野球中にハムストリングスを肉離れ…私が学んだ回復までの道のり
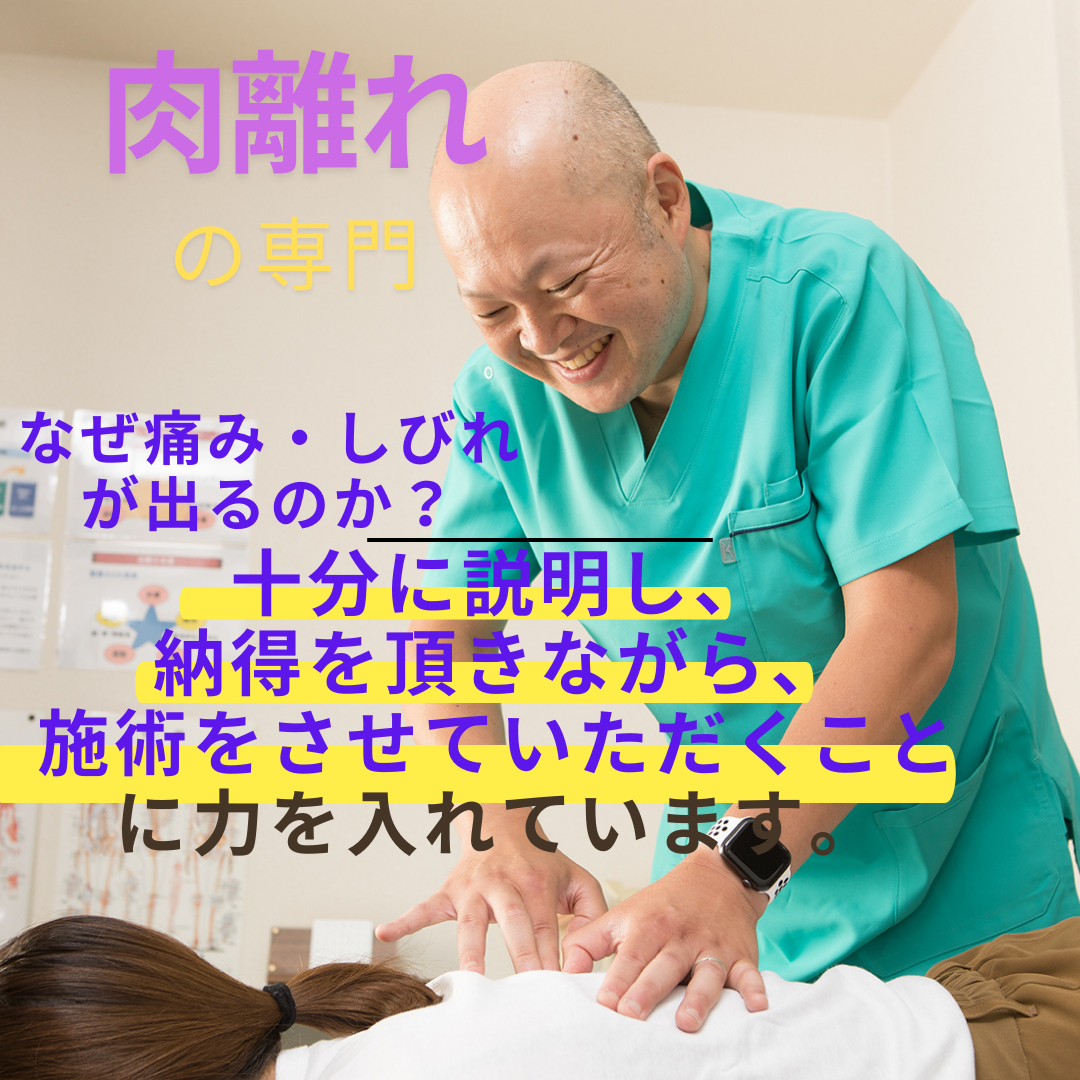
【体験談】野球中にハムストリングスを肉離れ…私が学んだ回復までの道のり
先週の日曜日、少年野球の練習でランナーとして参加していた際、セカンドベースを回った瞬間にハムストリングス(太ももの裏)を肉離れしてしまいました。
この記事では、私の現在進行形の体験を、「同じケガで悩む方の力になれるように」できるだけ具体的にまとめます。
ハムストリングス肉離れをした瞬間の体験
ベースを回った瞬間、後ろから誰かに蹴られたような衝撃とともに「ブチッ」と音がしたような感覚。
「つったのかな?」と思いましたが、すぐに違和感が強まり、その後は歩くのがやっとで走ることはできませんでした。
肉離れとは?一般的な原因と仕組み
ハムストリングスは「大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋」で構成され、ダッシュ・ジャンプ・方向転換で強く働く筋群です。
強い負荷がかかったとき、筋線維が部分的に断裂するのが肉離れです。
- 急なダッシュやストップ動作
- 疲労や柔軟性不足
- ウォーミングアップ不足
…と一般的には説明されますが、私の場合は少し事情が違うと感じています。
私の場合:
左膝の可動域制限や感覚鈍麻(しびれ)があり、筋力も弱い状態でした(現在もトレーニングを継続中)。
そのため、右の殿筋群やハムストリングスに負担が偏りやすいことは把握していました。
正直、最近はその部位の補強トレーニングをサボっていたことも反省点です。
同じ「肉離れ」でも、背景(可動域・神経症状・筋力差・フォーム)によって再発リスクは変わると実感しました。
ケガ直後に行った応急処置
直後に行ったことは以下の通りです(いわゆるRICE処置)。
- Rest(安静): まずは動かさず楽な姿勢で座る
- Ice(冷却): 氷で20分程度冷却(過冷却に注意)
- Compression(圧迫): 包帯で軽く圧迫
- Elevation(挙上): 心臓より少し高く挙上
早く行うほど腫れや内出血を最小限にできる一方、損傷グレードによっては方法・強度の調整が必要だと感じました。
今回の私はグレードⅠ(軽度)に相当。冷却直後に筋が硬くなり、帰り道で歩行がつらくなる場面も。固定も強すぎると痛みが増すため、痛みが悪化しない範囲で「弱め〜中等度」に留めました。
病院と整骨院(接骨院)での対応・治療
病院では「軽度の肉離れ」との診断。主に湿布・包帯/テーピングでの対応でした。
一方、整骨院(接骨院)では物理療法の選択肢が多く、私のケースでは以下を実施しました。
- 超音波+ハイボルテージ電気のコンビネーション施術
- 3Dメンズ(微弱電流)施術
いずれも炎症・疼痛の軽減や日常生活の早期回復をサポートする目的で行い、実際に痛みの軽減・動作のしやすさを感じました。
なお、上記は保険適用外(自費)で、目安:1回2,500円(保険+自費で3,500円程度)。※当院の料金の一例です。
「肉離れは安静だけで放っておけば治る」と考えられがちですが、早期の痛み・炎症コントロールと、その後の再発予防プログラムで回復の質は変わります。
私は「日常生活に支障が出ない」ことを短期目標にし、無理なく段階を踏みました。
リハビリのステップ(私の実例)
- 痛み最優先期: 歩行の確認、腫れや熱感の確認、軽いアイソメトリック(痛みが出ない範囲)
- 可動域改善期: ハムストリングスを痛みが出ない範囲でゆっくり伸ばす/神経モビライゼーションを慎重に
- 筋力回復期: ヒップリフト・グルートブリッジ・クラムシェル等で殿筋群を中心に、片脚支持へ進行
- フォーム再学習: 走動作の股関節主導(腰椎過伸展を避ける/骨盤前傾のし過ぎに注意)
- 競技復帰準備: ランジ→サイドステップ→加速/減速→低速ダッシュ→中速→高速へ段階的に
「焦らないこと」が最大のコツ。下半身に痛みがある日は上半身中心のトレーニングに切り替えるなど、やれることを続けるとメンタルも安定します。
再発予防のポイント(臨床+体験から)
- ウォームアップ徹底: 体温・関節可動域・神経系の準備まで意識
- 柔軟性の維持: ハムストリングスだけでなく、股関節周囲の柔軟性も
- 殿筋群と体幹の強化: 腰部の安定と股関節主導のフォーム確立
- 左右差の是正: 可動域や感覚の左右差を把握し、個別化トレーニングで補正
- 痛みの我慢はしない: 違和感段階で調整=膝・足部の連鎖もチェック
体験から伝えたいメッセージ
ケガ直後は「早く復帰したい」と焦りました。しかし、焦りは再発の近道であることを身をもって学びました。
もしこの記事を読んでいる方が何度も同じ部位を肉離れしてしまうなら、リハビリ設計やトレーニングの考え方を見直すサインかもしれません。
背景(可動域・神経症状・筋力差・フォーム)まで含めて一緒に整理すると、回復の質と再発予防が変わります。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 肉離れはどのくらいで治りますか?
A. 目安として、軽度は2〜3週間、中程度は1〜2か月、重度は3か月以上かかる場合もあります。
ただし個人差が大きく、リハビリ内容や復帰時期の見極めで変わります。
Q2. 放置しても自然に治りますか?
A. 自然に痛みは引くことが多いですが、筋力・柔軟性・フォームの課題が残ると再発しやすいです。段階的な復帰計画をおすすめします。
Q3. 施術を受けるメリットは?
A. 炎症・疼痛の軽減、回復過程の見える化、再発予防プログラムの個別設計が可能になります。
物理療法(超音波/ハイボルテージ/微弱電流など)は、日常生活の早期回復のサポートが期待できます。
Q4. いつ走り始めてもいい?
A. 痛みゼロ=即全力ではありません。等速→軽いドリル→低速→中速→高速へと段階を踏み、翌日の痛みが悪化していないかを指標に進めます。
関連記事のご案内
LINEから気軽に相談・予約できます
肉離れでお困りの方へ。放置は再発のもと。まずは現状の評価と、あなたに合った段階的プランを一緒に作りましょう。
LINEなら24時間ご予約・ご質問を受け付けています。
まとめ
- 肉離れは誰にでも起こりうるが、背景要因の整理が再発予防のカギ
- 応急処置はRICEが基本。ただしグレードに応じて強度を調整する
- リハビリは段階的に・客観指標(痛み/可動域/翌日の反応)で進める
- 殿筋群・体幹・股関節主導のフォーム再学習でパフォーマンスと予防を両立
私の体験が、同じケガで悩む方の背中を少しでも押せたら嬉しいです。ケガは予防するものです!ケガをしてしまったら必ず治療しましょうね





